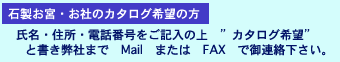![]()
| 当社の石製外宮は、他社とは明らかに異なります。 |
| オーダーメイド製品と呼べようかと思います。 |
| 長期間の使用に耐えるようパーツ数を減らし、塊石から削り出す方式で造りました。 |
| 製造中の細かなチェックはもちろん、納品まで何度も厳しい検品を行いますし、 |
| 使い勝手が良くなるいくつかの改良も加えてあり、ご満足頂けるものと思います。 |
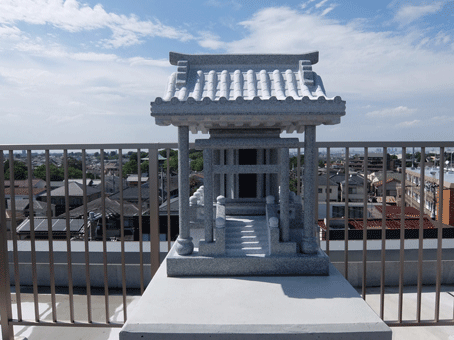

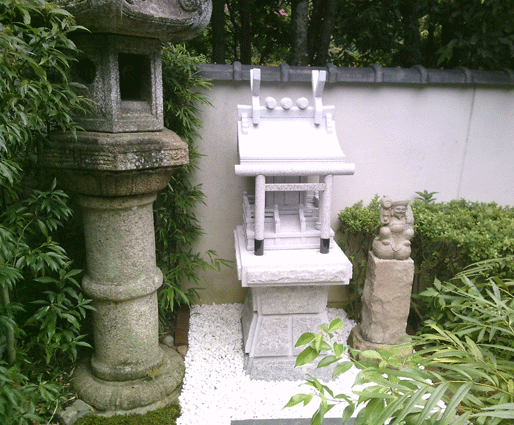
| 御影石製の外宮(お宮 or お社)は、年月の経過とともに黒ずんできますが、 |
| 木製と違い腐りませんし縮んだり反ったりしない半永久的なものです。 |
| お稲荷さんを祀る”お社”と土地神様を祀る外宮(お宮 or お社)、は同じものを |
| 使用します。地域により、お祀りする方の好みにより外宮の形は決まります。 |
| お宮(お社)は神様の居住空間であり、神様およびゆかりの物 |
| (ご神体、神像、おふだ等)を収容し、お祀りする建築物です。 |
| 胴部(火袋部)---扉がついている部分は左右に扉部が開きその奥に収納物を保管する |
| 仕組みになります。 |
| 従来は、四角い御影石の塊(かたまり)の中心部を上部からコアにより |
| 円筒状に抜き、その部分が室内としていました。 |
| 弊社では、従来の胴部を円筒状に抜く方法に加え、手間がかかるので行っていなかった |
| 角状に抜くという方法を行っています。これにより胴部の収容力は倍増しました。 |
| また、扉部の表面に閂(かんぬき)及び閂受けを設ける事により扉内の収容物も |
| 安全に保たれます。 |
| お宮には、屋根正面部左右と正面階段下部脇を結ぶ左右の柱(丸柱または角柱) |
| が付属します。 この柱上部に注連縄(しめなわ)を結んだりします。 |
| 外宮部は基本的に、屋根部、胴部、階段・回廊を含む基礎部、左右柱部の5ツのパーツ |
| で出来ています。それぞれのパーツは原石からの削り出しで出来ています。 |
| (高級型お宮は小さな鳥居等が加わります) |
| 弊社では設置前に以下の事、確認させて頂き別途有料ですが対応させて頂いております。 |
| ★ 建立月日・建立者の好みの書体での彫り込み |
| ★ 胴部室内の拡張(収納物---ご神体、御札等の大きさにより) |
| ★ 風対策で神具(榊立て等)の設置部分の掘り下げ |
| 個人のお客様、直接の問い合わせ歓迎します。 |
| 既存お宮・お稲荷さん(石製、金属製、木製、コンクリート製)の解体、運搬、廃棄等 |
| についても、ご相談下さい。 |
|
2026年(令和 8 年) 初午の日は 02月01日(日曜日)です。
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏神様、鎮守様 と 産土神そして稲荷神 |
| 氏神様は、文字通り一族の神をさします。古くは、先祖代々生まれてから死ぬまで同じ場所で過ごすのが |
| 普通でした。 |
| 他の土地に生活の場を移すことはもとより、旅行することもなく代々同じ場所に住んで、そこで生まれて |
| 育って死んでゆく。というのが当然のことでした。つまり、その一族を守る神様(氏神)と、その土地を守る |
| 神様(鎮守神)、そこで生まれた子供を守る神様(産土神=うぶすなのかみ)が同じだったのです。 |
| ところが、時代が変わると生活パターンが変化してきました。育った土地で子供を生むとは限らなく |
| なってくるし、家族全員が一緒に住むとは限らなくなります。つまり、代々住んできた土地の神様は |
| 一族の守り神として氏神となり、現在住んでいる土地の神様が鎮守神、生まれた土地の神が産土神と別々に |
| なったのです。しかし、時代が進むにつれ氏神が、その土地を守る産土(うぶすな)神や鎮守神と |
| 混同されるようになってきました。 |
| 稲荷神(お稲荷様、お稲荷さん)は、元々は穀物を司る農業神でありましたが、江戸時代には農業神、食物神、 |
| 殖産興業神、商業神、屋敷神として、農村だけでなく都市部でも祀られるようになりました。 |
| 主祭神はまちまちで(神道では・・宇迦之御魂神うかのみたま、豊宇気毘売命 とようけびめ、保食神 |
| うけもち、 大宣都比売神 おおげつひめ、若宇気売神 わかうかめ、御ケツ神 みけつ |
| 仏教では・・真言密教の影響で ダキニ天)が主祭神とされています。 |
| お稲荷さん というと 狐 を思い浮かべますが、神様の指示で働く神獣、つまり使い動物なのです。 |
| 古来から神聖視されてきた 狐(霊狐/白狐)を従える稲荷神は庶民に受入れやすかったのではないでしょうか。 |
| 神道上の稲荷神社の総本社は京都市伏見区にある伏見稲荷大社ですが、仏教寺院でもある豊川稲荷のような |
| 神社もあります。 |
| 我が国では古来から土地神信仰が行われてきましたが、支配層は、伝来してきた仏教にも魅力を感じ、 |
| 結果”神仏習合”という超(ちょう)玉虫色の 神様を信ずるのも良し、仏様を信ずるのも良し、 |
| 神社の敷地内に寺があることも、或いは寺の敷地内に神社があることも良しとしたところによります。 |
| 明治時代までは神社の儀式をお坊さんがとりおこなったり、逆もあったそうです。 |
| では、なにゆえ江戸時代にお稲荷さんは流行したのでしょう。徳川家8代将軍徳川吉宗(有名な暴れん坊将軍) |
| が、紀州家から、徳川宗家を継ぐ時に連れてきた家臣のなかにお稲荷さんの信奉者がいたこと。 |
| 有名な奉行 大岡越前守は赤坂一ツ木の自邸に守護神として祀っていました。 |
| また、吉宗とともに移ってき、小姓から老中に上り、しかも3人の将軍のもと最後は5万7千石まで出世をした |
| 田沼意次も邸内に社を設け、信奉している ・・ というのが知れると、あやかりたいと考える |
| 武家の庭内に祠を建てる人が急増したようです。 |
| 出世のみならず開運・商売繁盛などのご利益があることから、商人などの町人の宅地でも祀られるようになり |
| 江戸では大流行したようです。 |
| ▼ 胴部(火袋部)の大きさ詳細 (わら屋根型お宮、高級型お宮 小叩き仕様・本磨き仕様、出雲型お宮) |
| お宮を決めるとき、形状等の外観も大事ですが、何を収容するかを考えることも大事です。 |
| 石製お宮の収納所である胴部は、強度と製作効率の良い円柱形にくり抜く丸コア抜きで造られて |
| きました。余裕ある収納部には程遠いものでした。弊社ではコア抜き穴を拡張し四角室内と |
| しました。また夜間時などには扉を開かぬ様に閂(カンヌキ)が掛かる様にしています。 |
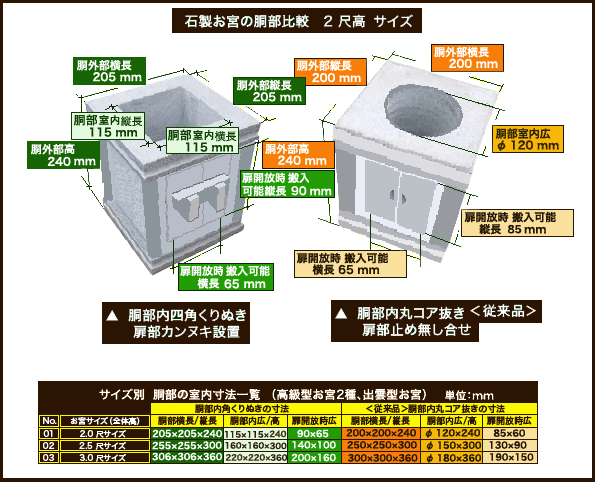
 |
 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
 |
|
|||||||||||
|
|
| ▼ 御札の種類と大きさ |
| お宮を決めるとき、外観の比較も重要ですが、収容力もよく検討してみませんか?というのも導入後 |
| 御札、御本尊様、 が収まらない等の話を結構聞くからです。収容物を納める胴部自体の丈(高さ) |
| が 2尺サイズ丈の石製お宮では胴部丈は240 mmぐらいとなります。一般的な紙札の丈は245 mm |
| なので室内に入りきらずとりあえず御札の寸詰めをした等の話しを聞きます。 |
| 弊社では胴部丈の伸張、屋根部と胴部、胴部と胴部下の基礎部の接面の掘削について相談に |
| 応じています。 |
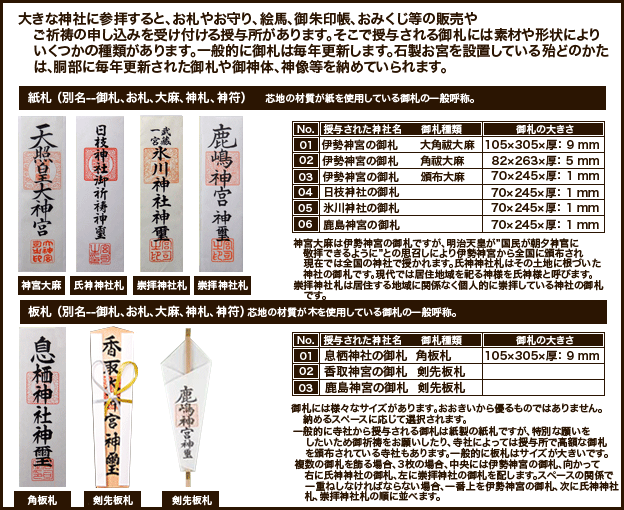
| New ▼ 高級型お宮(白御影石製) 小叩き仕上げ(両外壁本磨き仕上げ)の詳細と施行写真 |
| ご注文〜施工完成まで 約2.0ヶ月と お考え下さい。 |
| 分割(屋根部、胴部、欄干・階段・基礎部及び柱2本中柱)されたパーツを |
| 施工場所に運び、接着はボンド主体に行い目地詰め、クリーニングして完成です。 |
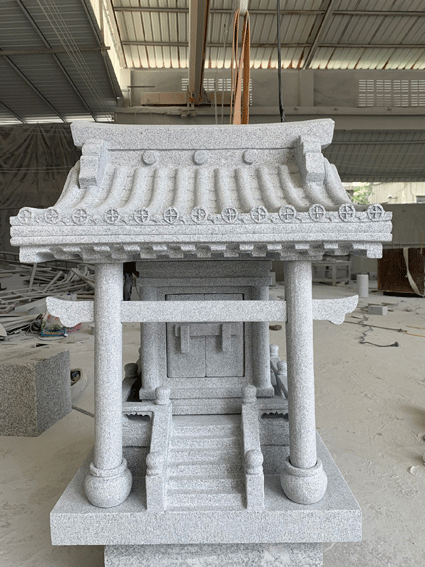 |
 |
|||||||
|
|
|||||||
 |
||||||||
|
||||||||
 |
 |
|||||||
|
|
|||||||
 |
 |
|||||||
|
|
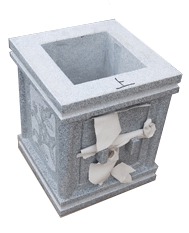 |
|
|
▲高級型お宮 小叩き仕様Gタイプの 胴部内四角刳貫き形 扉止めアリ |
外観は磨き部を入れず落ち着いた見栄えの 小叩き仕様の高級型お宮ですが、その中でも 胴部室内を四角く刳り貫き扉と一体の閂(かんぬ き)止めを採用したGタイプは強風時や気圧が急激 に変動するときにも扉は勝手に開きません。 (胴部側面への仕上げは小叩き仕上げとなります)
|
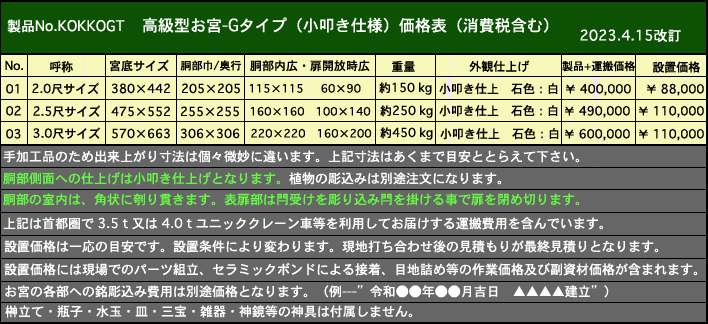
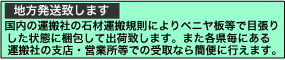
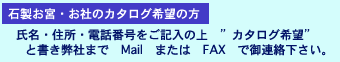
| ▼ 高級型お宮(白御影石製) 小叩き仕様/本磨き仕様 ミニ鳥居含む |
| ご注文〜施工完成まで 約2.0ヶ月と お考え下さい。 |
| 5つに分割(屋根部、胴部、欄干・階段・基礎部及び柱2本)されたパーツと |
| 小さな鳥居を施工場所に運び、ボンド主体に組み立て接着をして目地詰め、 |
| クリーニングして完成です。 |
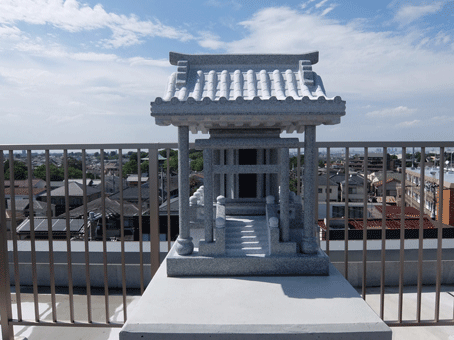 |
||||
|
||||
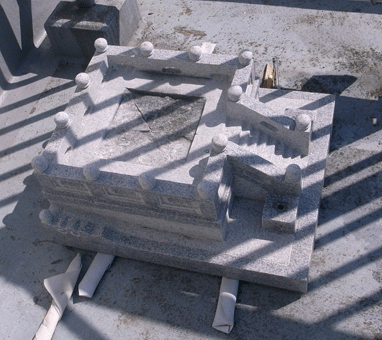 |
||||
|
||||
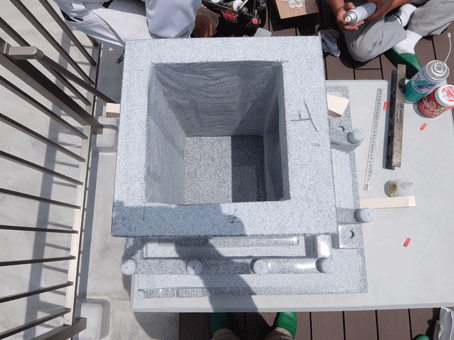 |
||||
|
||||
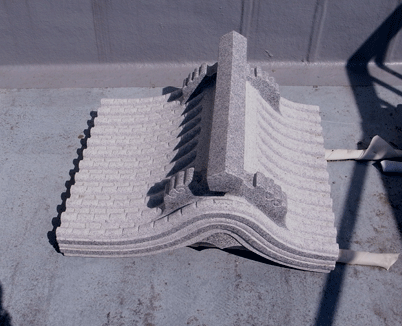 |
||||
|
||||
|
|
||||
  |
||||
|
||||
 |
||||
|
||||
| ▼ 高級型お宮 施工写真 | |||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
 |
|
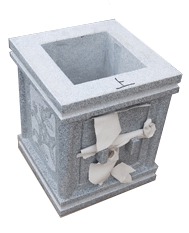 |
|
| ▼ 高級型お宮本磨き仕様Gタイプの胴部
胴部内四角刳り貫き 扉止めアリ |
外観は小叩き仕上げの中アクセントに本磨き仕上げを 効果的に使う高級型お宮です。 側面には椿のレリーフが彫り込まれ 階段上り口には小鳥居がセットされます。 胴部室内は四角く刳り貫かれ、 扉と一体の閂(かんぬき)止めを採用した Gタイプは強風時や気圧が急激に変動するときにも 扉は勝手に開きません。(胴部側面への仕上げは 椿のレリーフが彫り込まれます)
|
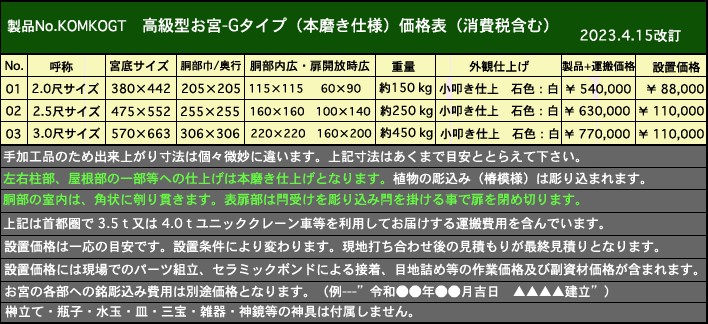
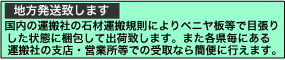
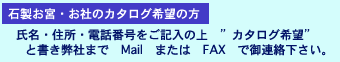
| ▼ 出雲型お宮(白御影石製) 叩き仕上げ |
| ご注文〜施工完成まで 約2.0ヶ月と お考え下さい。 |
| 6つに分割(屋根部、屋根飾り、胴部、欄干・階段・基礎部及び柱2本)されたパーツを |
| 施工場所に運び、ボンド主体に組み立て接着をして目地詰め、クリーニングして完成です。 |
 |
 |
||||
|
|
||||
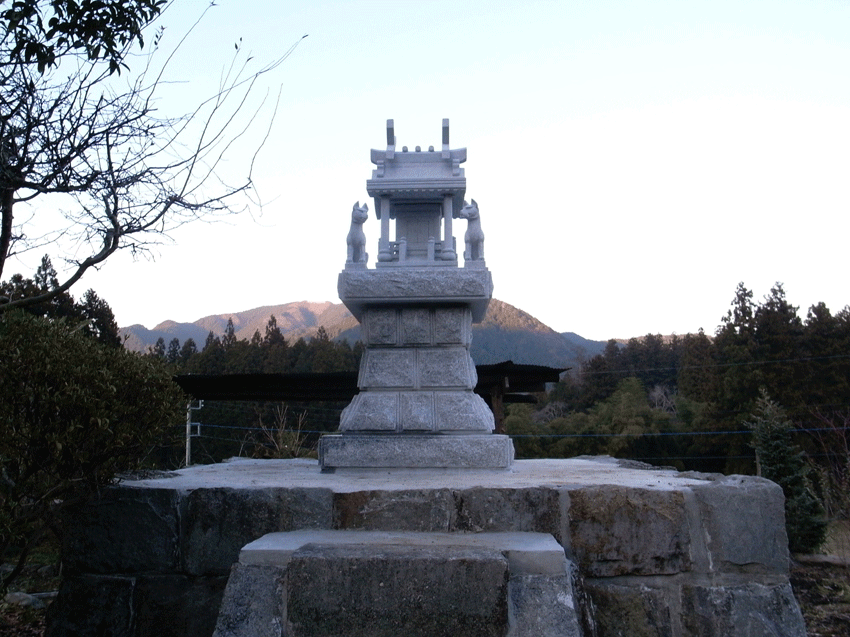 |
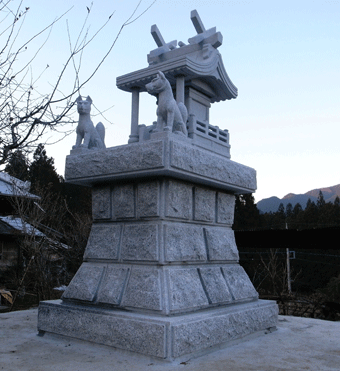 |
||||
|
|
||||
 |
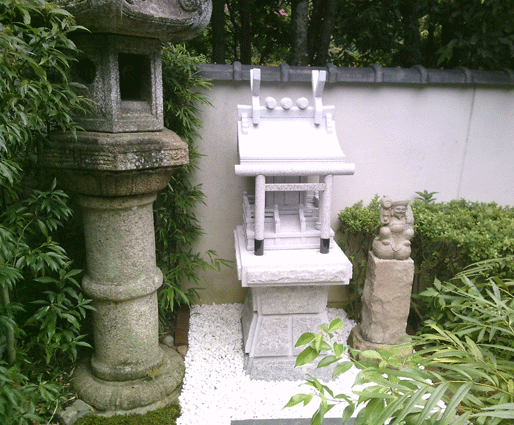 |
||||
|
|
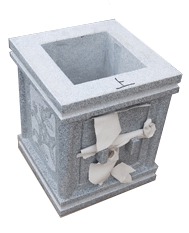 |
|
| ▼ 出雲型お宮 Gタイプの胴部
胴部内四角刳り貫き 扉止めアリ |
外観は小叩き仕上げです。 扉と一体の閂(かんぬき)止めを採用した Gタイプは、強風時や気圧が急激に変動するとき にも扉は勝手に開きません。 (胴部側面への仕上げに 椿のレリーフは ありません)
|
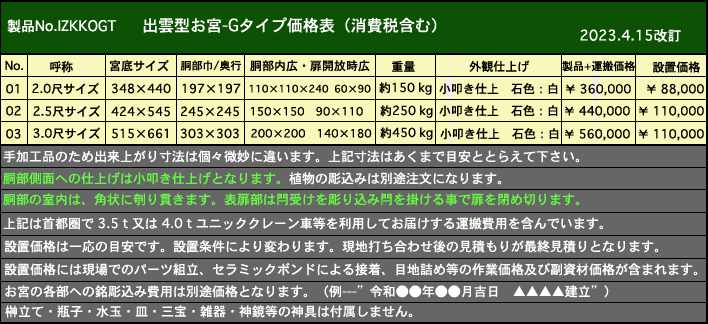
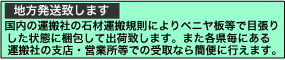
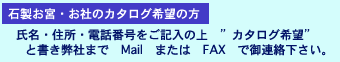
| ▼ わら屋根型お宮 (白御影石製) 小叩き仕上げ施工例 |
| ご注文〜施工完成まで 約2.0ヶ月と お考え下さい。 |
| 5つに分割(屋根部、胴部、欄干・階段・基礎部及び柱2本)されたパーツを施工場所に |
| 運び、ボンド主体に組み立て接着をして目地詰め、クリーニングして完成です。 |
 |
 |
|||||||
|
|
|||||||
 |
 |
|||||||
|
|
 |
 |
| ▼ わら屋根型お宮 Gタイプの胴部
胴部内四角刳り貫き 扉止めナシ |
外観は小叩き仕上げです。 強風時や気圧の変化による勝手な扉の開放を防ぐため 扉部の厚みは通常の1.5〜2.0倍の厚みに設定 しました。 (胴部側面への仕上げに 椿のレリーフは ありません)
|

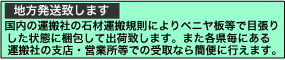
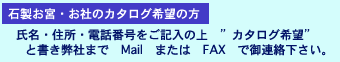
| ▼ 事業所(事務所/工場/倉庫/置き場)用 お稲荷さん |
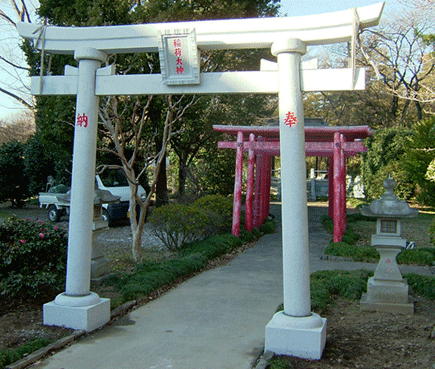 |
 |
||||||
|
|